
摂関政治は、平安時代に藤原氏が天皇を補佐しながら、実質的に政治を動かしていた体制のことです。摂政や関白として権力を握ったことから、こう呼ばれています。
このテーマは高校入試でもよく出題される重要キーワードです。今回は、摂関政治の仕組みや流れ、押さえておきたい人物や試験によく出るポイントを、わかりやすく解説します。
摂関政治ってなに?【基本を簡単に理解しよう】
摂関政治(せっかんせいじ)とは、平安時代に藤原氏が摂政や関白という立場で天皇を補佐し、実際の政治を動かした仕組みのことです。
- 摂政: 天皇が幼いときに、天皇に代わって政治を行う役職です。
- 関白: 天皇が成人した後に、天皇を助ける役職です。
いずれの役職も藤原氏が独占し、天皇の母方の親戚(外戚)として絶大な影響力を持っていました。この体制により、藤原氏は何代にもわたって実権を握り、朝廷で圧倒的な権力を振るうことになります。
入試では「誰が最初の摂政・関白か」「どんな仕組みか」といった問題がよく出るので、ここでしっかり押さえておきましょう。
どうやって藤原氏が権力を持ったの?【流れで理解】
摂関政治が始まった背景には、藤原氏の巧みな政治戦略と外戚としての立場があります。ここでは、藤原氏がどのようにして権力を手に入れ、摂政・関白として政治の中心に立ったのかを、3人の人物に注目して見ていきましょう。
藤原良房|初の摂政としてスタートを切る
858年、清和天皇がまだ幼くして即位したとき、藤原良房(ふじわらのよしふさ)が日本で初めての摂政に就任します。さらに866年の「応天門の変」では、ライバルであった伴善男(とものよしお)を失脚させ、藤原氏の地位を確固たるものにしました。
藤原基経|初の関白で仕組みを完成させる
884年には藤原基経(もとつね)が光孝天皇のもとで初の関白に任命されます。これにより、天皇の年齢に関係なく藤原氏が政治を主導できるようになり、摂関政治の体制が完成しました。
藤原道長と頼通|摂関政治の最盛期へ
その後、藤原道長(みちなが)は自分の娘を次々と天皇に嫁がせ、「この世をば我が世とぞ思ふ…」と詠んだほどの権力を手にします。息子の藤原頼通(よりみち)も約50年にわたり関白を務め、摂関政治は最盛期を迎えました。
試験で差をつける!摂関政治の重要ポイント3選
摂関政治は、平安時代の政治の中でも入試でよく問われるテーマです。特に次の3つのポイントをしっかり押さえておくことで、得点アップにつながります。
① 摂政と関白のちがい
摂政は、天皇が幼いときに代わって政治を行う役職です。一方、関白は天皇が成人しても補佐する立場です。いずれも藤原氏が独占し、実権をにぎりました。
② 外戚としての藤原氏の戦略
藤原氏は、自分の娘を天皇に嫁がせて「外戚(母方の親族)」となり、政治に強い影響を持ちました。この戦略が摂関政治の土台となります。
③ 摂関政治の終わり方
1068年、後三条天皇が「親政」を始め、1086年には白河天皇が「院政」を始めます。こうして藤原氏の力は弱まり、摂関政治は終わりを迎えました。
摂関政治が終わった理由とは?【流れで整理】
摂関政治は、長く藤原氏が権力を握る政治体制でしたが、やがて終わりを迎えます。その理由は、天皇自身が政治の実権を取り戻そうとしたからです。
まず1068年、後三条天皇が即位し、自分の手で政治を行う「親政(しんせい)」を始めました。これにより、藤原氏の影響力が弱まります。
さらに1086年には、白河天皇が上皇となり、「院政(いんせい)」という新しい政治のしくみを始めました。天皇が退位後も政治を行うことで、藤原氏の出番は減っていきました。
このように、天皇自身が政治の中心に戻ったことで、摂関政治は終わりを迎えたのです。
まとめ|摂関政治のポイントをしっかり整理しよう
摂関政治は、藤原氏が摂政や関白として天皇を補佐し、実質的に政治を動かしていた平安時代の政治体制です。外戚としての立場を活かし、長く権力をにぎりましたが、親政と院政の始まりによって終わりを迎えました。
要チェックポイント:
- 摂政と関白の違いを理解しよう
- 藤原良房・基経・道長・頼通の流れを覚える
- 外戚政治のしくみを確認
- 応天門の変が藤原氏台頭のきっかけ
- 親政と院政が摂関政治の終わりを意味する
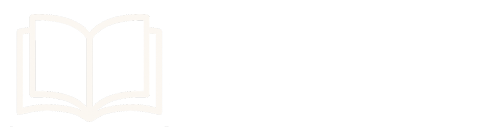

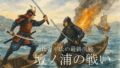
コメント