
【鎌倉幕府の成立】源頼朝が築いた武士政権
鎌倉幕府の成立とは?
「鎌倉幕府の成立」とは、日本の武士による初めての政権である「鎌倉幕府」がどのようにして誕生したのかを指します。 これは日本の歴史において非常に重要な転換点であり、それまでの貴族中心の政治から、武士が主導する新しい時代への幕開けを意味しています。 この記事では、鎌倉幕府の成立の背景から流れ、ポイントまでをわかりやすく解説します。
鎌倉幕府成立の背景:なぜ武士の時代になったのか?
平安時代の後期、日本の政治は貴族が独占していました。しかし、地方では治安が悪化し、盗賊や反乱が多発。朝廷(天皇や貴族)では対処できず、各地で武士が力を持つようになりました。
特に、伊豆や関東地方で力を伸ばしていた源頼朝(みなもとのよりとも)が大きな役割を果たします。彼は平氏政権に反発し、やがて武士をまとめていきました。
源平合戦と鎌倉幕府の成立
1180年、以仁王(もちひとおう)の令旨(りょうじ)を受けた源頼朝は、平氏打倒を掲げて挙兵します。これが源平合戦の始まりです。
この戦いで頼朝は関東を拠点にし、1185年の壇ノ浦の戦いで平氏を滅ぼします。源義経や源範頼などの協力もあり、頼朝の勢力は全国に広がっていきました。
そして、1192年(いいくに作ろう鎌倉幕府)に、源頼朝が征夷大将軍に任命され、鎌倉に幕府を開きました。これが「鎌倉幕府の成立」です。
鎌倉幕府ってどんな仕組み?
鎌倉幕府は、それまでの貴族による中央政治とは異なり、武士による武士のための政権でした。頼朝は「守護(しゅご)」や「地頭(じとう)」を全国に置き、土地の管理や治安維持を任せました。
- 守護:国ごとに設置。治安維持や軍事を担当。
- 地頭:荘園や公領の管理、年貢の取り立てを担当。
これにより、武士たちは幕府から役職や土地を与えられることで、幕府に忠誠を誓う仕組みが生まれました。
鎌倉幕府成立の意義
鎌倉幕府の成立は、日本の歴史上初めて、武士が中心となって政治を行う体制が確立したという点で重要です。 これにより、以後の室町幕府や江戸幕府など、武家政権が日本の政治の中心となる時代が始まります。
また、朝廷と幕府が並び立つ「二重政権」とも言われる体制が生まれ、政治のバランスや対立も今後の歴史に影響を与えることになります。
鎌倉幕府の成立年は本当に1192年?
歴史教科書では「いいくに(1192)作ろう鎌倉幕府」と覚えますが、実は1185年を成立とする説もあります。この年、源頼朝は守護・地頭を設置し、実質的に全国支配を始めているからです。
しかし、形式的な意味での「征夷大将軍」任命が1192年なので、これを正式な成立とするのが一般的です。
まとめ:鎌倉幕府の成立を一言で!
- 成立年:1192年(または1185年とも)
- 成立者:源頼朝
- 理由:武士の力が強まり、平氏を倒して自ら政権を築いた
- 意義:武士による初の政権で、日本史の大きな転換点
鎌倉幕府の成立を理解することで、日本の中世社会の始まりや、武士の役割を深く知ることができます。 受験対策や日本史の基礎知識として、しっかり押さえておきましょう!
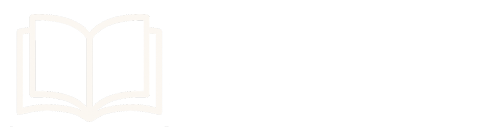
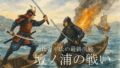

コメント