
金閣寺を建てた足利義満|室町幕府の黄金時代を築いた将軍
足利義満は、室町幕府の第3代将軍として、日本の歴史に大きな足跡を残した人物です。特に、あの有名な金閣寺を建立したことで知られています。彼は南北朝の混乱を収拾し、明(中国)との貿易を活発化させるなど、室町時代の政治、経済、文化を大きく発展させました。この記事では、足利義満の素晴らしい功績を深掘りしていきます。
若くして将軍に就任した足利義満
足利義満は1358年に、第2代将軍である足利義詮の子として生まれました。そして、父の死後、なんと10歳という若さで将軍職を継ぐことになります。
当初は周りの有力な家臣たちが政治を補佐していましたが、義満は成長するにつれて自ら積極的に政務を執り行うようになります。彼のリーダーシップは、後の室町幕府の繁栄の礎となっていきました。
終わりのない南北朝時代を統一
義満が将軍になった当時、日本は「南北朝時代」という大混乱のさなかにありました。京都に「北朝」、奈良の吉野に「南朝」という2つの朝廷が存在し、激しく争い合っていたのです。
義満はこの長きにわたる争いを収拾するため尽力し、1392年に南北朝の統一を達成します。これにより、国内の混乱が収まり、室町幕府の権力はかつてないほど強固なものとなりました。日本の平和を取り戻した義満の功績は、計り知れません。
明(中国)との「勘合貿易」で経済を発展させる
足利義満は国内の安定だけでなく、国際交流にも目を向けました。特に力を入れたのが、当時の中国王朝である「明」との貿易です。これは「勘合貿易」として知られています。
勘合とは、正式な貿易船であることを証明する割符(わりふ)のこと。これを持つ船だけが明との貿易を許され、安定した交易が可能になりました。この貿易によって、日本は経済的に大きく発展し、中国の進んだ文化や貴重な品々が日本にもたらされ、人々の暮らしを豊かにしました。
「北山文化」の象徴、金閣寺の建立
足利義満の文化面での功績といえば、やはり京都にある金閣寺(鹿苑寺)を抜きには語れません。この豪華絢爛な建物は、もともと義満の別荘でしたが、彼の死後にお寺に改められました。
この時代の文化は「北山文化」と呼ばれ、義満が支援したことで能や茶の湯といった芸術が大きく発展しました。特に、能を大成させた観阿弥・世阿弥親子を保護し、能楽が武士のたしなみとして広まるきっかけを作ったことは、日本の芸能史における大きな功績です。金閣寺は、この北山文化の華やかさを今に伝える代表的な建造物として、世界中の人々を魅了し続けています。
天皇をも超えようとした野望
強い権力と影響力を持った足利義満は、「日本国王」と名乗るなど、将軍でありながら天皇のような振る舞いをすることもありました。これは朝廷からは快く思われず、義満が亡くなった後には「日本国王」の称号が禁止されるほどでした。
しかし、この行動は、義満がいかに自分の力を確立し、日本の最高権力者として君臨しようとしていたかを示すものです。
足利義満の死、そして室町幕府の「黄金時代」
足利義満は1408年に50歳でこの世を去りました。その後、息子の足利義持が将軍職を継ぎますが、義満ほど積極的な政治手腕を発揮することはありませんでした。
義満が将軍として国を導いた時代は、室町幕府が最も栄え、安定した「黄金時代」と評されています。彼の強力なリーダーシップと多岐にわたる功績が、その後の日本の発展に大きな影響を与えたことは間違いありません。
まとめ:足利義満のすごい功績
足利義満は、日本の歴史を語る上で欠かせない重要人物です。彼の功績を改めて振り返ってみましょう。
- 10歳で将軍になり、卓越した政治手腕を発揮した。
- 南北朝の分裂を終わらせ、日本を統一に導いた。
- 明(中国)との勘合貿易を推進し、国の経済を発展させた。
- 金閣寺を建立し、能や茶の湯が花開いた北山文化を創り上げた。
- 将軍として、日本の歴史を大きく動かした唯一無二の存在である。
「金閣寺」といえば足利義満!と覚えておけば、歴史の授業やテストでも役立つはずです。
金閣寺や足利義満以外にも、高校入試によく出る室町時代のポイントをまとめた記事があります。
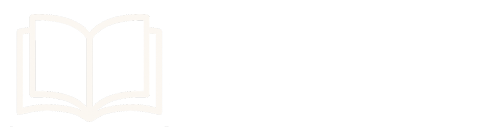



コメント