
承久の乱:朝廷VS幕府!武家政権確立への転換点
承久の乱とは?
承久の乱(じょうきゅうのらん)とは、1221年(承久3年)に後鳥羽上皇が鎌倉幕府を倒そうとした戦いのことです。結果は、幕府が勝利し、朝廷の政治的な力は大きく弱まりました。この乱をきっかけに、武士による政治が全国的に広がっていきます。
承久の乱の原因は?|上皇と幕府の対立
鎌倉幕府の成立と朝廷の不満
源頼朝が1192年に鎌倉幕府を開いてから、日本は武士が政治の中心となる時代に入りました。しかし、京都の朝廷(天皇・上皇)は依然として政治的な影響力を持ち続けており、両者の間には緊張がありました。
後鳥羽上皇は、朝廷の権威を取り戻そうと考え、次第に幕府に対して不満を募らせていきます。
北条氏による「執権政治」の成立
3代将軍・源実朝の死後、幕府の実権は北条政子やその兄・北条義時ら北条氏の手に移ります。これにより「執権政治(しっけんせいじ)」が本格化し、上皇の政治介入はますます難しくなりました。
承久の乱の経過|どんな戦いだった?
後鳥羽上皇、ついに挙兵!
1221年、後鳥羽上皇は「北条義時を討て」という命令(宣旨)を全国に出し、反幕府勢力を結集して挙兵します。これが承久の乱の始まりです。
幕府の迅速な対応と勝利
北条政子は御家人たちに「頼朝公の恩を思い出してください」と演説し、多くの武士が幕府側につきました。幕府軍は京都に進軍し、上皇側の軍勢を圧倒。わずか1ヶ月ほどで戦いは終結し、後鳥羽上皇は敗北します。
承久の乱の結果|政治の主導権が完全に幕府へ
上皇の流罪と朝廷の弱体化
敗れた後鳥羽上皇は隠岐(おき)に流され、そのほかの関係者も処罰されました。朝廷の政治的影響力は大きく後退し、実質的に幕府が日本の支配者となったのです。
六波羅探題の設置と幕府の支配拡大
幕府は京都に「六波羅探題(ろくはらたんだい)」という役所を設け、西国の武士や貴族を監視しました。また、乱に参加した貴族の土地を没収し、功績のあった御家人に分配することで、幕府の支配は全国に及ぶようになりました。
承久の乱の意義とその後の日本
承久の乱は、日本史のなかでも特に重要なターニングポイントです。この戦いを通じて、天皇・上皇による政治(貴族中心の時代)は終わりを迎え、武士の時代が本格化します。
その後の日本は、鎌倉・室町・江戸と武家政権が続き、明治時代まで武士が政治の中心であり続けました。
まとめ|承久の乱はなぜ重要なのか?
承久の乱は、「なぜ武士が日本の支配者になったのか」を理解するうえで欠かせない出来事です。朝廷と幕府の対立、後鳥羽上皇の挑戦、そして幕府の勝利によって、日本の政治構造は大きく変わりました。
承久の乱=武士による本格的な政権掌握の始まりと覚えておきましょう。
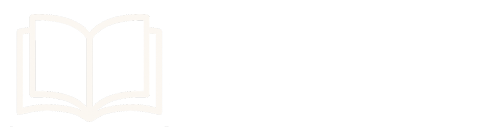


コメント