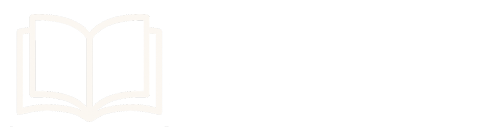鎌倉時代は高校受験の日本史で頻出! **「どこから手をつければいいか分からない…」「覚えることが多すぎる…」**と感じていませんか?
源頼朝、北条氏、元寇、御成敗式目…。入試によく出る用語はたくさんありますが、すべてを丸暗記するのは大変ですよね。
この記事では、高校受験によく出る鎌倉時代の「超重要ポイント」を6つに厳選! 鎌倉時代の流れとセットで、得点に直結する知識を効率よく身につけられるように、中学生にもわかりやすく解説します。
難しい用語もたった6つのポイントに絞ることで、鎌倉時代の全体像をスムーズにつかみながら、日本史の得点アップを目指しましょう!
鎌倉時代とは?|武士が政治の主役になった時代
鎌倉時代は、日本で初めて武士が政治の中心に立った時代です。
それまでの平安時代では、天皇や貴族が国を治めていました。 しかし、源頼朝が鎌倉に幕府を開いたことで、政治の力が貴族から武士へと大きく移り変わったんです。
鎌倉幕府の仕組みは、将軍に仕える武士たちが、その見返りとして土地を与えられるという、武士独自の支配体制が特徴です。
この時代には、北条氏による執権政治やモンゴルの襲来(元寇)、さらには新しい仏教の広がりなど、日本史の中でも大きな転換点となる出来事がたくさんありました。
高校受験では、この**「武士政権の始まり」や「幕府の仕組み」**がよく問われます。まずは全体の流れをつかむことが、得点アップへの第一歩ですよ!
鎌倉幕府の成立【1192年】|源頼朝が開いた武士の政権
鎌倉時代の始まりは、**源頼朝(みなもとのよりとも)**が政治の実権を握ったことからスタートします。
平安時代の終わりには**平清盛(たいらのきよもり)**が権力を握っていましたが、源平合戦で平氏が滅び、代わって頼朝が力をつけました。
そして1192年、頼朝は朝廷から**「征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)」に任命され、現在の神奈川県にあたる鎌倉に鎌倉幕府を開いた**んです。
この出来事は、貴族の時代から武士の時代へと変わる、日本の政治にとってまさに大きな転換点といえます。
定番の語呂合わせ**「いい国(1192)作ろう鎌倉幕府」**は、入試でもよく出るので、しっかり覚えておきましょう!
鎌倉幕府では、将軍を中心に御家人(ごけにん)と呼ばれる武士たちが主従関係を結び、全国の支配が進められていきました。
日本で最初の本格的な武家政権として、鎌倉幕府の成立は日本史の中でも非常に重要な出来事です。
御家人制度と武士のしくみ|「御恩と奉公」でつながる関係
鎌倉幕府が安定した政治を行う上で、将軍と武士たちの信頼関係は非常に重要でした。その基盤となったのが、**「御恩と奉公(ごおんとほうこう)」**という制度です。
将軍に仕える武士は**「御家人(ごけにん)」**と呼ばれます。
御家人は、戦いの際には将軍のために戦ったり、幕府の命令に従ったりします。これが**「奉公」**です。
そしてその見返りとして、将軍から領地を与えられたり、土地を守る権利を与えられたりします。これが**「御恩」**です。
このように、将軍と御家人はお互いに支え合う関係であり、このつながりが鎌倉幕府の政治の基盤でした。
また、幕府は全国に**「守護(しゅご)」や「地頭(じとう)」**という役職を置き、治安の維持や年貢の徴収を行わせました。
「御恩と奉公」の仕組みは、武士による政治がどのように成り立っていたのかを理解する上で大切なポイントです。高校受験でも頻出なので、しっかり覚えましょう!
承久の乱で朝廷より幕府が強くなる|上皇と武士の争いとは?
鎌倉時代の大きな出来事の一つが、**承久の乱(じょうきゅうのらん)**です。これは、朝廷と鎌倉幕府が対立した大規模な戦いでした。
当時、天皇の政治を裏で支えていた**後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)**は、幕府の力が強くなったことに不満を抱いていました。
そして1221年、幕府を倒そうと兵を集めて戦いを仕掛けたのです。これが承久の乱でした。
しかし、戦いは幕府側の勝利に終わり、後鳥羽上皇は島流しにされてしまいます。
この勝利によって、**「天皇や上皇よりも、武士の政権が上になった」**ことが全国に示されることになりました。
さらに幕府は、朝廷を監視するために京都に**「六波羅探題(ろくはらたんだい)」**という役所を設け、武士による支配をいっそう強めました。
承久の乱をきっかけに、鎌倉幕府の力が全国に広がり、武士の時代が本格化したんです。高校受験でもよく出るテーマなので、背景と結果をセットで覚えましょう!
執権政治と御成敗式目|北条氏が幕府を動かしたしくみ
源頼朝の死後、将軍の力は徐々に弱まり、代わりに幕府の実権を握ったのが北条(ほうじょう)氏です。
北条氏は**「執権(しっけん)」という役職に就き、将軍を補佐する立場から政治の中心になっていきました。これが「執権政治」**といいます。
中でも有名なのが、3代執権の北条泰時(やすとき)です。彼は、武士の社会にふさわしい法律として「御成敗式目(ごせいばいしきもく)」を1232年に定めました。
これは日本で最初の武士のための法律で、土地の争いや家の相続などを公平に決めるルールとして使われました。
御成敗式目がつくられたことで、幕府の政治がより安定し、武士の支配体制が整ったといえます。
このように、将軍ではなく**執権が政治を動かす「執権政治」**は、鎌倉時代の重要な特徴の一つです。
高校受験では、**「北条氏」「執権政治」「御成敗式目」**がセットでよく出題されるので、しっかり理解しておきましょう!
元寇(モンゴル襲来)|2度の危機と幕府のゆらぎ
鎌倉時代の大事件といえば、「元寇(げんこう)」と呼ばれるモンゴル軍の襲来です。
元寇は、当時中国にあった**「元(げん)」という国の皇帝フビライ・ハン**が、日本に服従を求めてきたことがきっかけでした。
幕府はこれを拒否し、1274年と1281年の2回にわたって、モンゴル軍が日本に攻め込んできたのです。
1回目は**「文永の役(ぶんえいのえき)」、2回目は「弘安の役(こうあんのえき)」**と呼ばれます。
特に弘安の役では、激しい戦いの中で大きな台風がモンゴル軍の船を沈め、日本を守ったとされ、「神風(かみかぜ)」伝説が生まれました。
しかし、敵を追い払ったあと、活躍した御家人(ごけにん)たちへの恩賞(ほうび)が十分に与えられなかったため、彼らの間で不満が広がります。
このことで、御家人の経済状態が悪化し、結果的に幕府の力が弱まる原因にもなりました。
高校受験では、**「元寇の原因・2つの戦い・その後の影響」**が問われやすいポイントです。流れとセットで覚えましょう!
鎌倉新仏教の広まり|乱れた時代に心のよりどころを求めて
鎌倉時代は戦いや不安が多く、人々の暮らしも大きく変化しました。そんな中で生まれ、広まったのが**「鎌倉新仏教(かまくらしんぶっきょう)」**と呼ばれる、新しい仏教の教えです。
それまでの仏教は、貴族や一部の人たちだけのものでした。しかし、鎌倉新仏教は庶民や武士にもわかりやすく、より身近な教えとして広まりました。
特に有名なのが、以下の人物と宗派です。
- 法然(ほうねん): 念仏を唱えれば救われる**「浄土宗」**を開きました。
- 親鸞(しんらん): 悪人でも救われる**「浄土真宗」**を開きました。
- 日蓮(にちれん): 南無妙法蓮華経を唱える**「日蓮宗」**を開きました。
- 栄西(えいさい)・道元(どうげん): 座禅を重視する**「禅宗」**を開きました。
これらの新しい仏教は、人々が不安な時代を生き抜くための心のよりどころとなりました。
また、武士の生き方とも合っていたため、特に禅宗は多くの武士に支持されました。
高校受験では、**「それぞれの宗派の教えや開いた人物」**を区別して覚えることが重要です。
鎌倉新仏教は文化の面からも、鎌倉時代の特徴としてしっかり押さえておきましょう。
厳選!鎌倉時代の超重要用語10選【高校受験対策】
鎌倉時代は高校受験でもよく出る重要テーマです。この記事では、試験に頻出の超重要用語を10個に厳選し、わかりやすくまとめました。
| 分類 | 用語 | ポイントの概要 |
|---|---|---|
| 幕府の始まり | 源頼朝 | 鎌倉幕府を開いた武士。征夷大将軍に任命され、日本初の武家政権をスタート。 |
| 幕府の成立 | 鎌倉幕府 | 1192年に設立。武士が政治の中心となる時代が始まる。「いい国(1192)」で暗記。 |
| 支配のしくみ | 御恩と奉公 | 将軍と御家人の主従関係。恩賞と奉仕で結ばれる幕府の支配の基本。 |
| 地方支配 | 地頭・守護 | 幕府が地方に置いた役職。年貢徴収・治安維持を担当。全国支配のカギ。 |
| 幕府vs朝廷 | 承久の乱 | 1221年、後鳥羽上皇の反乱。幕府が勝ち、朝廷より幕府の方が強いと示す出来事。 |
| 幕府の実権 | 執権政治 | 北条氏が将軍の代わりに政治の中心となる。実権は「執権」に集中。 |
| 法律の整備 | 御成敗式目 | 1232年に北条泰時が制定。武士のための初めての法律。 |
| 外国との戦い | 元寇 | モンゴル軍が2度襲来(文永の役・弘安の役)。神風伝説や御家人の困窮が起こる。 |
| モンゴル側 | フビライ・ハン | 元の皇帝。日本に服従を求めて元寇を命じた人物。 |
| 宗教 | 法然 | 浄土宗の開祖。鎌倉新仏教の代表格。庶民に支持され「念仏で救われる」と説いた。 |
鎌倉時代の要点まとめ|流れとキーワードをおさえよう
鎌倉時代は、源頼朝が幕府を開いたことで武士の時代が始まりました。
御恩と奉公による主従関係、北条氏による執権政治、御成敗式目などの制度が整えられ、政治の仕組みが確立されます。
その後、元寇により幕府の支配は揺らぎますが、鎌倉新仏教の広まりなど、文化面でも大きな変化が見られました。
高校受験では、「流れ・人物・制度・外敵(元寇など)・宗教」の5つの視点から出題されます。
まずは用語を流れでつなぎ、何が起きたのかを理解することが、得点への近道です。
コツコツ覚えれば必ず点につながります。焦らず、自分のペースで、一つずつ確認していきましょう! 応援しています!