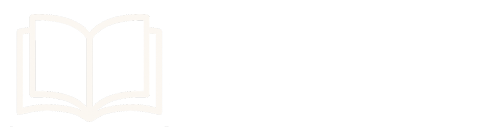室町時代(1338〜1573年)は、足利尊氏(あしかがたかうじ)が京都に室町幕府を開いたことから始まりました。
将軍が国をまとめ、各地の守護大名(しゅごだいみょう)が力を持つようになります。しかし、守護大名の中には戦国大名(せんごくだいみょう)になる人もあらわれ、全国で戦いが続きました。
文化では、足利義満(あしかがよしみつ)の金閣(きんかく)や、足利義政(あしかがよしまさ)の銀閣(ぎんかく)が代表的です。
応仁の乱(おうにんのらん)で幕府の力が弱まり、戦国時代へとつながっていきます。
室町時代とは?将軍と戦乱の時代をわかりやすく解説
室町時代とは、足利尊氏が京都に室町幕府を開いた1338年から、戦国時代へと移るおよそ150年間のことを指します。
この時代は、天皇が2つに分かれた南北朝時代から始まり、将軍の権力が弱まっていく中で、守護大名や戦国大名が力を持つようになりました。
また、室町時代には金閣などの文化が生まれ、貿易もさかんに行われましたが、後半になると応仁の乱が起こり、全国が戦乱に巻き込まれていきます。
政治・文化・外交が大きく動いたこの時代を理解することで、歴史全体の流れもつかみやすくなります。室町時代の特徴をしっかり押さえて、入試でも得点を狙いましょう!
そんな室町時代を入試で確実に得点するには、特に押さえておきたい重要な出来事や流れがあります。ここでは厳選した7つのポイントを紹介します。
室町幕府の成立と足利尊氏|建武の新政から幕府誕生までの流れ
室町幕府の始まりには、鎌倉幕府の滅亡と「建武の新政(けんむのしんせい)」の失敗が大きく関わっています。
1333年、後醍醐天皇(ごだいごてんのう)は、足利尊氏(あしかがたかうじ)らの協力を得て鎌倉幕府を倒し、自ら政治を行う建武の新政を始めました。
しかし、この政治は貴族や公家を重視する内容で、武士たちの期待を裏切るものでした。そのため武士たちの不満が高まり、やがて足利尊氏が後醍醐天皇に反旗を翻します。
尊氏は新たに光明天皇を立てて「北朝」を支持し、1338年には京都に室町幕府を開き、初代将軍となりました。幕府の所在地が京都・室町にあったことから、この時代を「室町時代」と呼びます。
足利尊氏が幕府を京都に開いたのは、政治の中心だった京都に近く、朝廷との距離を取りつつも影響力を維持しやすい場所だったからなんです。
この流れをつかむことで、室町時代の始まりがより明確に理解できます。
南北朝時代と朝廷の分裂|なぜ天皇が二人いたのか?
室町幕府の成立と同時に始まったのが、**南北朝時代(なんぼくちょうじだい)**です。この時代は、朝廷が2つに分かれ、約60年間にわたって対立が続いた特殊な時代でした。
鎌倉幕府を倒した後醍醐天皇は、自ら政治を行う「建武の新政」を始めましたが、武士の不満を買い、足利尊氏と対立。尊氏は新たに光明天皇を立て、京都に「北朝(ほくちょう)」を設けました。一方、後醍醐天皇は奈良の吉野に移り、「南朝(なんちょう)」を立てたのです。
つまり、同じ時期に天皇が2人いる「南朝」と「北朝」が並び立ったのが南北朝時代。これは日本の歴史の中でも特にめずらしい状況です。
戦いは何十年も続きましたが、最終的には北朝が正統とされ、1392年に3代将軍・足利義満の仲介によって南北朝の統一が実現しました。
この南北朝の分裂は、将軍の政治力と朝廷の関係性を理解するうえで超重要な出来事です。高校入試でも必ずと言っていいほど出題されるので、流れをしっかりおさえておきましょう!
守護大名の台頭と地方支配の強化|戦国時代につながる力の変化とは?
室町時代には、幕府から地方を治める役職として**守護(しゅご)が任命されました。もともとは治安維持などが役目でしたが、次第に力をつけていき、やがて守護大名(しゅごだいみょう)**と呼ばれる存在に変わっていきます。
守護大名は、田畑や住民を直接支配する「地頭(じとう)」などを従わせ、領地を広げながら政治・経済の実権を握るようになりました。特に有力な守護大名は、一つの国だけでなく複数の国を支配するケースもあり、まるで小さな王様のような存在に成長します。
このように、中央の幕府よりも地方の守護大名が力を持つようになったことが、後に戦国時代へとつながる大きな流れになります。将軍の命令が届きにくくなり、各地で独自に争いが起こるようになっていくのです。
守護大名の台頭は、室町時代を理解するうえで欠かせないキーワード。将軍の力が弱まる一方で、誰がどうやって地方を支配していったのかをしっかり覚えておきましょう。
足利義満と日明貿易(勘合貿易)|金閣を建てた将軍のもう一つの顔
室町幕府の第3代将軍・足利義満(あしかがよしみつ)は、政治力と経済力を高めた優れた将軍として知られています。義満の時代には、国内の混乱が一時的におさまり、幕府の力も最も強くなりました。
その義満が注力したのが、中国(明)との貿易=日明貿易(にちみんぼうえき)です。これは、日本と中国の間で正式な貿易を行うために、勘合符(かんごうふ)という通行証のような札を使って、正規の貿易船を区別する制度でした。このため、日明貿易は「勘合貿易」とも呼ばれます。
義満は、当時の明の皇帝に「日本国王源道義(にほんこくおう みなもとのどうぎ)」という名前で貢物を送り、その見返りとして絹織物や銅銭などを得ました。一方で、日本からは刀剣・硫黄・銅などが輸出されました。
この貿易によって幕府の財政は安定し、金閣(鹿苑寺)の建立など華やかな文化も発展しました。
足利義満と日明貿易は、室町時代の外交と経済の両面を理解するうえでとても重要なポイントです。
北山文化と金閣寺|武士と公家が生んだ室町文化の魅力とは?
室町時代の文化の大きな特徴は、武士の文化と公家の文化が融合したことにあります。これにより生まれたのが、室町文化(むろまちぶんか)と呼ばれる新しいスタイルです。
その代表が、3代将軍・足利義満の時代に栄えた北山文化(ほくざんぶんか)です。義満は、京都の北山に金閣寺(きんかくじ)=鹿苑寺(ろくおんじ)を建て、華やかで洗練された建築や芸術を生み出しました。金閣は、上層が金箔でおおわれた3層の建物で、今も京都の名所として知られています。
北山文化は、それまでの貴族的な美しさに、武士らしい力強さや実用性を取り入れた文化でもありました。この時期には、能(のう)や茶の湯(ちゃのゆ)、書院造(しょいんづくり)なども発展し、後の日本文化に大きな影響を与えます。
なぜこのような文化が生まれたのかというと、義満のもとで幕府が安定し、武士が経済力と政治力を手に入れたことで、芸術や文化に力を入れられるようになったからです。
北山文化は、武士と公家の融合が生んだ、室町時代を代表する文化のかたちです。入試では金閣寺や能がよく出るので要チェック!
室町文化には、この北山文化(3代・義満の時代)の後に、8代将軍・足利義政(あしかがよしまさ)の時代に発展した東山文化も重要です。
東山文化は、義政が建てた銀閣(ぎんかく)=慈照寺(じしょうじ)に代表され、豪華だった北山文化と異なり、禅宗(ぜんしゅう)の影響を受けた「わび・さび」を重んじる、質素で精神的な美が特徴です。
北山文化と東山文化をセットで覚えることで、室町文化全体の流れと、それぞれの違いが明確になり、入試でより得点しやすくなります。
応仁の乱と戦国時代の始まり|室町幕府が崩れたきっかけとは?
室町時代の後半に起こった応仁の乱(おうにんのらん)は、日本を大きく変えるきっかけとなった戦いです。1467年、8代将軍・足利義政(あしかがよしまさ)の後継ぎ問題をめぐって、幕府の有力者たちが対立。これに守護大名たちが巻き込まれ、全国規模の戦乱へと発展しました。
東軍(細川氏)と西軍(山名氏)に分かれたこの戦いは、京都を中心に約11年も続きましたが、決着がつかないまま終わってしまいます。この混乱により、幕府の力は大きく弱まり、政治の中心だった京都の町も荒れ果てました。
応仁の乱の最大の影響は、将軍の命令が届かなくなり、各地の守護大名が独自に争いを始めたことです。これがやがて、戦国時代(せんごくじだい)へとつながっていきます。
つまり、応仁の乱は単なる一つの戦いではなく、室町幕府が事実上くずれ、戦国の世へ移る大きな分岐点だったのです。
高校入試では、「応仁の乱」や「義政の後継問題」「戦国時代の始まり」がよく問われるので、時代の流れとセットで理解しておきましょう。
農村の発展と民衆の力|室町時代の村と一揆をわかりやすく解説
室町時代は、政治の中心が混乱する一方で、地方の農村(のうそん)では人々が力をつけていった時代でもあります。この時期、農民たちは協力し合って惣村(そうそん)と呼ばれる自治的な村をつくり、自分たちのルールで村を運営するようになりました。
惣村では、村の代表者を選び、年貢の分配や用水の管理などを話し合って決めるなど、民衆自身が地域をまとめる力を持ち始めます。また、祭りや行事を通して村のつながりも強まりました。
こうした中で、生活が苦しくなると、農民たちは力を合わせて土一揆(どいっき)を起こすようになります。特に、借金の帳消し徳政令(とくせいれい)を求める徳政一揆(とくせいいっき)がたびたび起こり、時には幕府や有力な寺社もその要求に応じるほどでした。
さらに、京都近くでは農民が団結して政治を動かす山城国一揆(やましろのくにいっき)も発生しました。これは民衆の力が高まった象徴ともいえる出来事です。
このように、室町時代は民衆が政治や社会に影響を与えるようになった重要な時代です。高校入試でも一揆や惣村の仕組みはよく出るので、しっかり理解しておきましょう。
室町時代で入試によく出る人物と用語7選【高校受験対策】
室町時代の中でも特に入試でよく出る人物や用語を、重要度の高い7つに厳選してまとめました。流れと一緒に覚えることで、得点につながります!
| 用語 | 解説(覚えるべきポイント) |
|---|---|
| 足利尊氏(あしかがたかうじ) | 室町幕府を京都に開いた人物。建武の新政に不満を持ち、後醍醐天皇と対立した。 |
| 建武の新政(けんむのしんせい) | 後醍醐天皇による政治改革。武士の不満がたまり、失敗に終わった。 |
| 南北朝時代(なんぼくちょうじだい) | 天皇が2つ(南朝・北朝)に分かれて争った時代。60年近く続き、義満によって統一された。 |
| 足利義満(あしかがよしみつ) | 室町幕府の3代将軍。南北朝統一、金閣の建設、日明貿易の開始など、政治・文化・外交の中心人物。 |
| 勘合貿易(かんごうぼうえき) | 義満が明と始めた貿易。勘合符という通行証を使って正式な貿易船を区別した。 |
| 応仁の乱(おうにんのらん) | 義政の後継争いと守護大名の対立で起きた全国的な戦乱。戦国時代の始まりとなり、幕府の力が大きく弱まった。 |
| 土一揆(どいっき) | 借金帳消し(徳政)などを求めて農民が起こした集団行動。惣村の発展と民衆の力の高まりを示す代表的な出来事。 |
室町時代のまとめ|入試で差がつく重要ポイントをおさらい!
室町時代は、足利尊氏による幕府の成立から、応仁の乱を経て戦国時代へと続く、日本の歴史の大きな転換期です。南北朝の分裂、守護大名の台頭、足利義満の外交・文化政策、そして民衆の成長など、さまざまな変化がこの時代に集中しています。
高校入試では、「誰が」「なぜ」「どうなったのか」という流れが問われやすく、単語の暗記だけでは得点につながりません。
室町時代は複雑に見えて、ポイントをおさえれば得点源になります!時代のつながりを意識して、何度も復習しましょう。