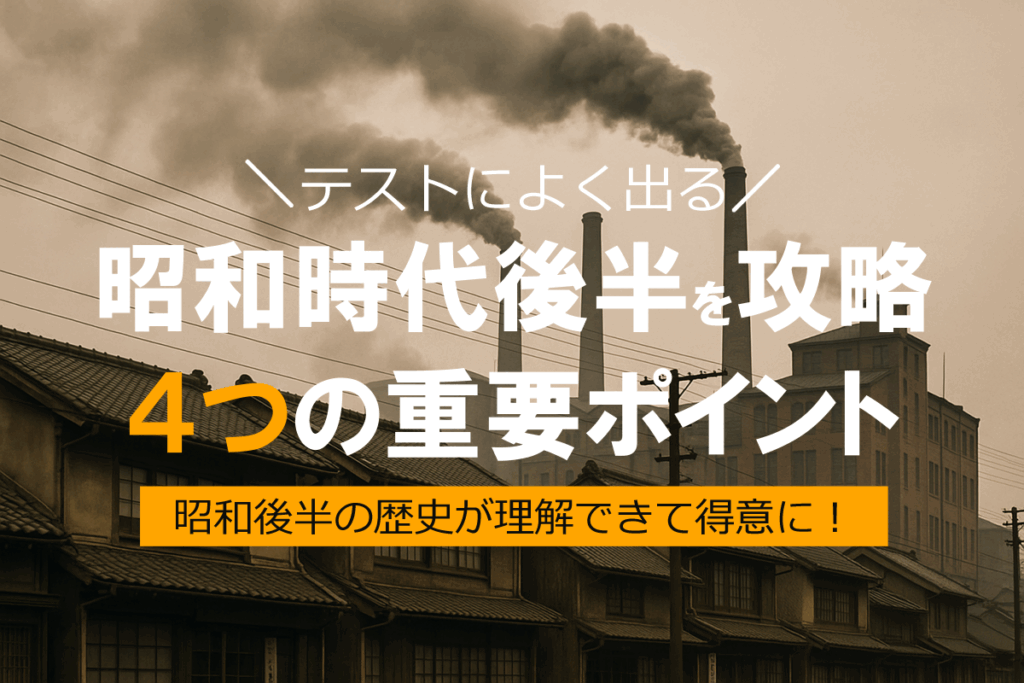
高校受験の日本史、覚えることが多すぎて困っていませんか?
なかでも昭和後半(1945〜1989年)は、戦後の復興から高度経済成長、そしてバブル期まで、日本が劇的に変化した時代です。そのため、高校入試でもよく出る重要単元なんです。
この記事では、昭和後半の歴史を「4つのテーマ」に分けて、流れで理解できるようにわかりやすく解説します。ただ暗記するのではなく、出来事のつながりと意味をしっかり押さえることで、昭和後半の歴史がグッと理解できて得意になりますよ!
1.戦後の改革と新しい憲法(1945〜1947)
GHQの占領下で始まった日本の再出発
1945年、第二次世界大戦が終わり、日本は敗戦による混乱の中にありました。
そんな中、日本に進駐してきたのが連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)です。GHQは、日本が二度と戦争を起こさない平和な国になるよう、多くの改革を指導しました。この時期は、日本の政治・経済・社会の仕組みを大きく作り直す「新しい国づくり」のスタートといえます。
日本国憲法と3つの基本原則
GHQの改革の中でも特に重要なのが、日本国憲法の制定です。1946年に公布され、翌1947年に施行されたこの憲法には、次の3つの基本原則が定められました。
- 国民主権:国の政治の主役は「天皇」ではなく「国民」であることが明確にされました。
- 平和主義:戦争を放棄し、戦力を持たないことが憲法に明記されました(第9条)。
- 基本的人権の尊重:すべての人に自由と平等の権利が保障されるようになりました。
また、天皇は政治の実権を持たず、「象徴」として位置づけられる象徴天皇制が導入されました。
教育・経済・社会の民主化改革
この時期には、憲法以外にも民主化を進めるさまざまな改革が行われました。
- 教育改革:男女共学が始まり、義務教育が6年から9年に延長されました。
- 農地改革:地主から農地を買い上げ、小作人だった農民に安く売り渡すことで、自作農を増やしました。
- 財閥解体:三井・三菱などの巨大企業グループを解体し、経済の力を一部に集中させないようにしました。
これらの改革によって、日本はより平等で自由な社会へと大きく変わっていきました。
高校入試でも頻出のテーマなので、GHQの役割や憲法の三原則をしっかり理解しておきましょう。
2.国際社会への復帰と日米関係(1951〜1972)
サンフランシスコ平和条約と日本の主権回復
戦後、日本はGHQの占領下にありましたが、いつまでも外国の支配が続くわけではありません。
1951年、日本はアメリカを中心とする48か国とサンフランシスコ平和条約を結びました。
この条約によって、翌1952年に日本は主権を回復し、国際社会の一員として再出発することができました。
この条約の締結により、日本は戦争による占領状態から抜け出し、独立した国家として世界と関わる立場を取り戻しました。しかし、その一方で安全保障に関する課題が残されました。
日米安全保障条約とアメリカ軍の駐留
同じ1951年、日本はアメリカと日米安全保障条約(安保条約)も結びました。
この条約により、日本国内にアメリカ軍が引き続き駐留することが認められたのです。これは、冷戦の中でアメリカが日本を「西側の拠点」として重視したためです。
日本にとっては、自国の防衛をアメリカに頼る形になりましたが、一方で平和憲法を維持しつつ、安全保障を確保するという意味でも大きな転機となりました。
沖縄返還とその背景
戦後、沖縄はアメリカの統治下に置かれていました。日本の他の地域が独立を果たしたあとも、沖縄だけは長くアメリカの支配が続いていました。
しかし1972年、ついに日本とアメリカの間で合意が成立し、沖縄は日本に返還されました。これにより、日本はようやく全国の領土を取り戻すことができたのです。沖縄返還は、戦後の復興と国際関係の大きな節目となりました。
サンフランシスコ平和条約や日米安全保障条約、沖縄返還は、すべて昭和後半の重要な出来事です。
高校入試にも頻出のテーマなので、流れを押さえておきましょう。
3.高度経済成長と国民生活の向上(1950年代〜1970年代)
朝鮮特需と工業の発展
1950年に始まった朝鮮戦争により、日本の経済は思わぬかたちで立ち直るきっかけをつかみます。
アメリカ軍が大量の物資を日本企業に注文したことで、工場の生産が活発になり、日本全体の景気が回復しました。この特需を朝鮮特需(ちょうせんとくじゅ)と呼びます。
この流れをきっかけに、鉄鋼や自動車、造船などの工業がどんどん発展し、日本は高度経済成長時代へと突入しました。
三種の神器の普及と暮らしの変化
経済の発展とともに、一般家庭の暮らしも大きく変化していきます。
1950年代後半から1960年代にかけて、テレビ・冷蔵庫・洗濯機の3つの家電が多くの家庭に広まりました。これらは「三種の神器(さんしゅのじんぎ)」と呼ばれ、生活の質を大きく向上させました。テレビでニュースや娯楽を見たり、冷蔵庫で食べ物を保存できるようになったりと、生活が便利で豊かになったのです。
東京オリンピックと新幹線・高速道路の整備
1964年に開催された東京オリンピックは、戦後の復興を世界に示す一大イベントとなりました。
この大会に合わせて東海道新幹線が開通し、高速道路も全国に整備されるなど、インフラが大きく発展しました。その結果、人やモノの移動がスムーズになり、日本経済の活性化にもつながったのです。
朝鮮特需から始まったこの時代は、工業の発展・生活の変化・交通の整備と、まさに日本が経済大国へと成長した時代です。この時期の出来事は、すべてが経済成長と深く結びついているので、その関連性を意識して覚えましょう。
4.社会問題とバブル経済(1970年代〜1980年代)
四大公害病と環境庁の設置
高度経済成長の一方で、深刻な問題も起こりました。それが公害問題です。
工場の排水や排煙によって、全国で健康被害が広がり、特に有名なのが四大公害病です。
熊本県の水俣病、富山県のイタイイタイ病などがその代表で、多くの人々が苦しみました。
このような問題を受けて、1971年に環境庁(現在の環境省)が設置され、環境を守るための法律や取り組みが始まり、国をあげて公害対策が進められるようになったのです。
石油危機と省エネ政策のスタート
1973年には、第一次石油危機(オイルショック)が発生。
石油の価格が急に高騰し、ガソリンや電気などのエネルギーが足りなくなる事態となりました。
これをきっかけに、日本では省エネ政策が進められ、電気製品や車もエネルギー効率を意識したものへと変化していきました。
バブル経済の始まりと特徴
1980年代後半、日本はバブル経済と呼ばれる好景気を迎えます。株や土地の値段が異常に上がり、企業も個人も大きな利益を得るようになりました。しかし、このバブルは一時的なもので、後に大きな崩壊を迎えることになります。
四大公害病・石油危機・バブル経済は、すべて昭和後半を代表する重要な出来事です。
昭和後半によく出る!重要用語まとめ表【10語】
高校入試でよく出題される「昭和時代後半(1945年〜1989年)」の重要用語まとめ表を作成しました。
| 用語 | 意味・ポイント |
|---|---|
| GHQ(連合国軍総司令部) | 日本を占領し、民主化を進めた組織。日本国憲法の制定にも関わる。 |
| 日本国憲法 | 1947年施行。国民主権・平和主義・基本的人権の尊重が三原則。 |
| サンフランシスコ平和条約 | 1951年に締結、翌年発効。日本が主権を回復し独立した。 |
| 日米安全保障条約 | 日本にアメリカ軍の駐留を認め、安全保障をアメリカに依存する内容。 |
| 朝鮮特需 | 朝鮮戦争中、日本が物資を供給して経済が急成長した。 |
| 三種の神器 | 高度経済成長期に家庭に広がった家電。テレビ・冷蔵庫・洗濯機。 |
| 東京オリンピック(1964年) | 復興を世界に示す場。新幹線や高速道路の整備が進んだ。 |
| 四大公害病 | 工場の排水などが原因。水俣病、イタイイタイ病など。 |
| 環境庁 | 公害問題に対応するため1971年に設置された行政機関。 |
| バブル経済 | 1980年代後半、株や土地の価格が異常に上がった好景気。のちに崩壊。 |
まとめ|昭和後半は「流れ」で覚えよう
昭和後半は、戦後の混乱から高度経済成長、バブル経済まで、日本が大きく変わった時代です。
今回、紹介した4つのテーマで歴史の流れを整理すれば、出来事の背景やつながりがよくわかり、理解も深まります。この時代に生まれた制度や文化は、現代の日本社会にもつながっている重要ポイントばかりです。
入試にもよく出る分野なので、単に年号を暗記するだけでなく、流れと意味をセットで押さえるようにしましょう!
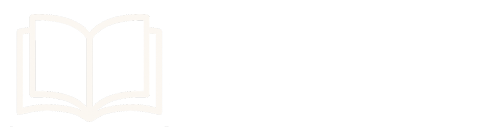
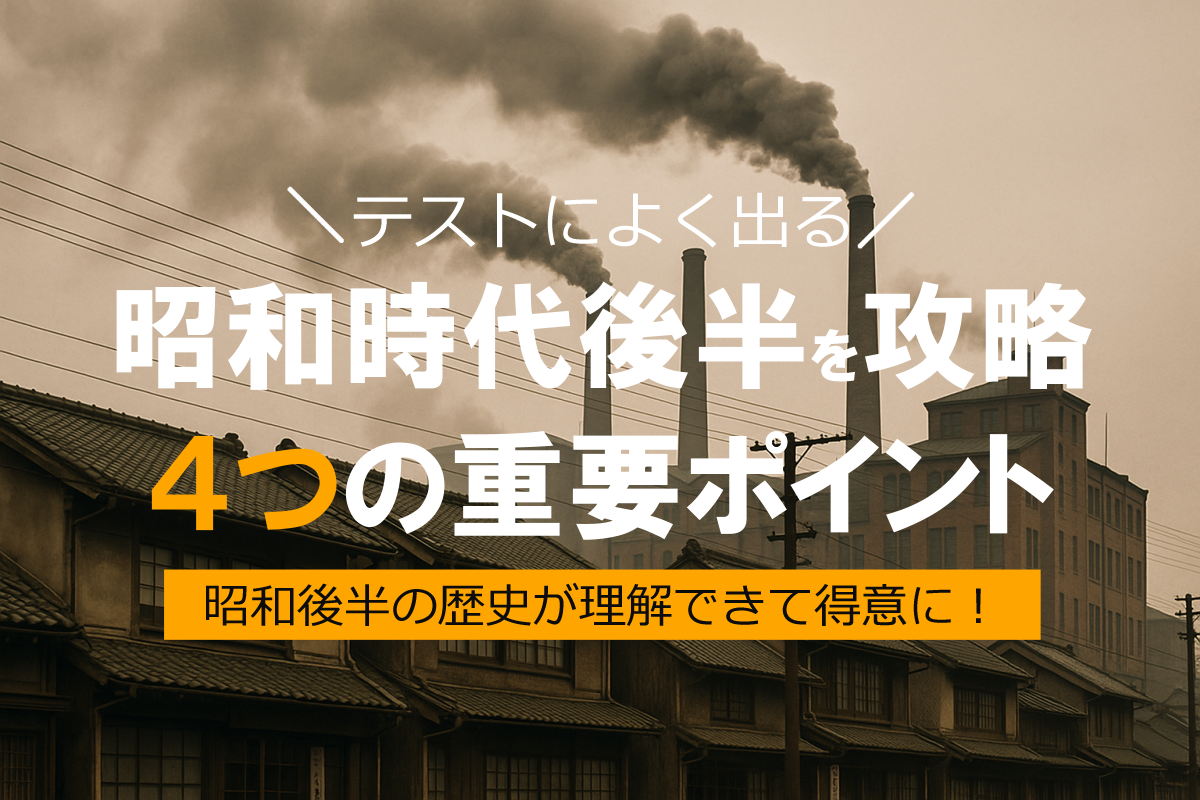
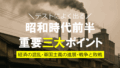
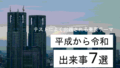
コメント